今回は都立両国高等学校附属中学・両国高校から東京大学に進学した女性が書いたものを私がコピペしたものです。
この女性はとても性格が良くて礼儀正しく、人として素晴らしい方です。
また、絵心もありオリジナルのLINEスタンプなども作っています。
なんとなく完璧な方に見えますが、実際に私には彼女の短所が見当たりません。
今回紹介する方は両国高校出身ですが、私の父方の祖父も両国高校出身なので親近感があります。
※適性検査を受けることは本来は「受検」ですが、ここでは「受験」としています。
自己紹介
はじめまして、ここでは、幼少期〜中学受験期を中心に、私がこれまでどのように勉強に取り組んできたのかをご紹介します。
この記事の内容はあくまで私個人の経験や意見に基づいたものですので、ご了承いただけると幸いです。
以下は私の簡単な経歴です。
・公立小学校6年の途中から塾→都立両国中高
・高校の2年間イギリス住み(2年の休学期間含め高校に4年在籍)
・東京大学理科Ⅰ現役入学→工学部→工学系研究科の大学院
・趣味は旅行と語学、Netflixやカラオケも好きです
幼少期の過ごし方
小学生の頃の趣味は、絵を描くことと、漫画や本を読むことでした。
読書家で漫画好きな父の蔵書が大量にある家で育ったので、大人向け・子供向けやジャンルはあまり気にせずとりあえず手に取った本を読んでいました。
低学年の間に読んでいたのは、児童文庫の小説が中心でした。
中・高学年になると『獣の奏者』シリーズ、『宇宙に秘められた謎』(スティーブン・ホーキング)、他には宮部みゆき作品など小説を中心に色々な本に手を出していました。
読書は親に勧められていたというより、いつも本を読んでいる父の真似をしていたら自然と好きになっていました。
父の蔵書の中でおすすめを尋ねると、父は嬉しそうに何冊も本を渡してくれました。
受験を決める前の家庭学習は学校の宿題をするのみで、覚えている限り一度も父と母が「勉強しなさい」と言うのを聞いたことがありません。
趣味も習い事も、基本的に私が自分でやりたいと言い出したもの以外は特に勧められず、かなりのんびり自由に育てられていたと思います。
ただし、週一回のスイミングだけは、当時の私の希望を無視して小学2年生ごろから始めました。
外遊びは人並みにする子どもだったのですが、スイミングスクールは好きになれず、毎週かなり嫌がりながら通っていました。
両親としては、たとえ好きでなくても最低限の体力をつけることが大切だと考えていたそうです。
私も今となっては、小さいうちに体力づくりをさせてくれた両親にとても感謝しています。
結局、小学校の間に通った習い事はスイミングスクールだけでした。
中学受験
中学受験を考え始めたきっかけは、5年生の半ばごろにあった小学校担任との三者面談でした。
もともと両親も私自身も全く受験を視野に入れていなかったのですが、私の小学校での成績がよく、勉強や読書が好きな様子だったことから、担任の先生が都立両国の受験をおすすめしてくださいました。
先生が両国を選んだのは、私立受験を始めるには時期が遅かったことと、距離的に通いやすかったことが理由でした。
当時の友だちに受験組が多く、私自身も勉強が好きだったので、私は受験自体には前向きでした。
ただ、どうしても受験して中学に入りたいというほどの強い思いはなく、地元の中学に進学するのも選択肢の一つだと考えていたので、都立両国単願を選びました。
父と母は他の学校について調べたり文化祭に連れて行ってくれたりもしましたが、私が志望校を決めた後は私の希望を応援して支えてくれました。
受験を決めて最初に始めたのは、父による家庭内受験対策講座でした。
文章を書く仕事をしている父が、「お父さん問題」と名付けて私に作文問題を出し、添削してくれていました。
強制力が弱いので私の提出頻度はまちまちでしたが、週に1−2回程度は真面目に添削を受けていました。
もともと文章を書くのも読むのも好きだった私は、比較的早い時期から適性検査Ⅰ(読解・作文)だけなら過去問に太刀打ちできるようになりました。
適性検査Ⅱ(算数・理科系問題)については、市販の過去問や対策問題集を買って少しずつ傾向をつかんでいきました。
こちらは作文ほど簡単にはいかず、問題によって出来にかなりブレがあったと思います。(現行の適性検査Ⅲは当時まだ導入されていませんでした)
小6に上がると、クラスで塾通いをする子が増え、私は友達の真似をして塾に通いたいと言い出しました。
両親はどちらも塾に通った経験がなく(塾長注:お父様は旧帝大卒)、私が通うことにもあまり肯定的でなかったのですが、最終的には折れて地元の小規模な小・中学生向けの塾に通わせてもらうことになりました。
塾を始めた6年生の7月ごろから、公立中高一貫校対策コースで週に2回、2-3時間の授業を受けて、家では宿題をやりました。
そのうち週1回は適性Ⅱの対策で、主にこちらに重点的に取り組んでいました。
宿題の量はそこまで多くなく、週に3-4時間程度家で取り組めば終わる量だったと思います。
わからない問題は基本的に父に質問して教えてもらっていました。
母は受験勉強に直接口を出すことがほとんどありませんでしたが、塾のお弁当やその他小学校や塾に必要な道具の準備も全てサポートしてくれました。
私は塾で順調に成績を伸ばし、9月と12月ごろに受けた公中検模試では合格圏判定をもらいました。
理系問題はまだ苦手もありましたが、作文が得意だったおかげで、9月の模試では総合成績で女子1位を取りました。塾のクラスは少人数で、自然と仲良くなったので、楽しく通っていました。
直前期は過去問の復習に励んで、二月についに本番を迎えました。
初めての受験で会場の雰囲気に緊張した上、私の受験した年の問題は例年と少し毛色が違ったので、解答欄は埋めたもののとても不安な気持ちで提出したのを覚えています。
終わった後は、迎えに来てくれた母と美味しいパスタを食べました。
両国中学・高校について
中学では、テニス部に入部しました。私はあまり気が進まなかったのですが、ここでも両親の体力第一の教育方針で半ば強制的に運動部を選ぶことになりました。
幸い友達に恵まれたので、テニス自体はそこそこ頑張りながら、部活動は卒業まで続けました。
両国中高の同級生は、(もちろん個人差はありますが)本を読むのが好きだったり、自分の趣味や興味を持っていたりと、自分の世界がある人たちが多かったように感じます。
趣味が共通する友達どうしで集まっていて、いい意味でお互いを気にしすぎずに共存している印象です。少なくとも私にとっては、とても居心地の良い環境でした。
勉強面では、中学生の間は特に目標もなかったので、宿題やテスト勉強を人並みにこなしていました。両国での教育に特色があるとすれば、英語教育だと思います。
中学生の授業はオールイングリッシュで、文法自体を教える授業はほとんどなく、例文を通して自然と文法を身につけるカリキュラムでした。
私はこの方針がとても合っていたので、授業を通して英語が好きになりました。
授業以外で特別何かしたわけではないので、ペラペラに喋れるようにはなりませんでしたが、中3の初めには英検2級に合格できました。
高校に入ってからは引き続き英語による授業と、受験対策の文法や長文読解の日本語による授業が半々程度になりました。
高校受験対策にとらわれず中学の間にこういった英語教育を受けられるのは、中高一貫校の大きな利点だと思います。
海外移住と東大受験
高校一年生の秋頃に、父が仕事でイギリスに海外赴任することが決まりました。
私は外国に住んで英語の勉強をすることに憧れがあったので同行に大いに賛成し、結果として妹を含む家族全員での引っ越しが決まりました。
2年間海外に滞在したことで、学年が一つ下がりました。高校2年の4月に渡英して、2年後に帰国すると、私の同級生はちょうど受験を終えて卒業する時期です。
そこで、私は学年を一つ下げて、帰国後に高校三年生として両国高校に戻ってくることにしました。
そうすれば、日本で受験勉強する期間が1年間確保できると考えてのことです。
赴任先では、現地の私立高校や語学学校に通いました。
渡英直後の私の英語力はネイティブとすらすら会話できるレベルではなく、最初の数ヶ月は聞き取ってなんとか答えるのが精一杯でした。
高校で友達ができて、授業にも慣れるうちにだんだん会話もできるようになりました。
2年経って帰国するころには、大学受験英語ならどんな問題でも太刀打ちできるレベルまで英語力が育ちました。(塾長注:東京大学英語二次試験106/120点)
1年間、受験生としてひたすら勉強するうちに、なんとか数学など英語以外の科目も周りに追いついてきました。
ここでも、仲良くなったクラスメイトのおかげで、忙しい中でも楽しく最後の学校生活を送れました。志望校はなかなか決められずにいましたが、11月ごろに、英語力を活かして受験できる東大を選びました。
最後に
私が学校での勉強や学校生活を楽しめたのは、友だちに恵まれたからでした。
留学先では私の拙い英語に耳を傾けて一緒に過ごしてくれる友だちに会ったことで、英語力や、自分と異なる言語や文化への興味が育ちました。
また、大学受験生になったばかりの時期は、遅れを取り戻そうと焦っていた中、編入した学年のクラスメイトと仲良くなったことで、かなり気持ちが楽になりました。
一緒に目標を立てて勉強してくれた彼女たちがいなければ、私の受験生活はこんなに充実したものにはならなかったでしょう。
夜遅くまで自習室を開けて、質問に親身に答えてくださった高校の先生方にもとても感謝しています。
最後に、私が新しい環境や学びを楽しめる人間になったのは、両親のおかげです。
両親は基本的に、勉強も習い事も進路も(スイミングと運動部以外は)全て私の意思に任せて、私が決めたことを応援してくれました。
小さい頃から私が興味を持ったことや得意だったことを伸ばしてサポートしてくれたおかげで、自分の努力や挑戦を肯定できるようになったのだと思います。
唯一強制された運動部に入る選択も、今では良かったと思っています。体力がなければ、大学での研究や趣味の旅行も十分に楽しめないからです。
長くなりましたが、個人的に私が大事だと思っているのは次の二点です。
・勉強や読書を続けるには、いっしょに取り組む家族や友だちを見つけて楽しむこと
・運動は、たとえ楽しくなくてもある程度続けるべきだということ
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コピペここまで。
塾長によるまとめ
私がこの手記を読んだ感想をまとめます。
この女性およびその環境についてはいくつかの特長があります。
・親からの強制はほとんどない。
・ただし本人がやりたいといったら親は全力でサポートしている。
・好奇心が強い。(高学歴の方のほとんどがそうです。)
・周りへの感謝の気持ちが強い。
これらは高学歴の方に多くあてはまることなので、何かの参考になれば幸いです。
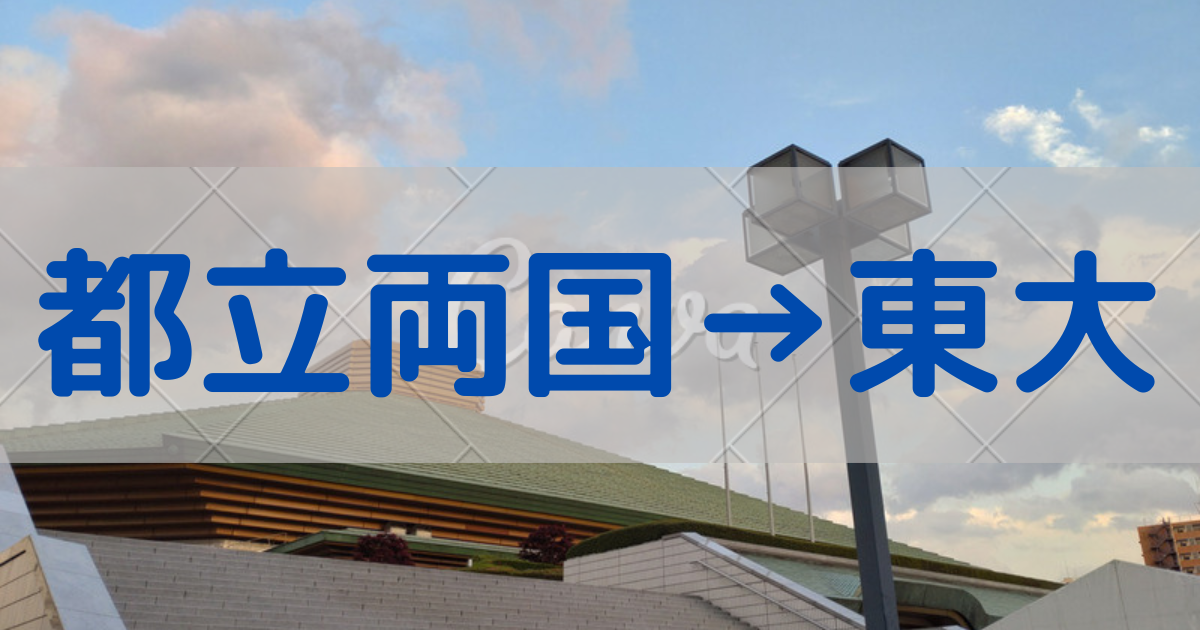










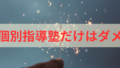
コメント