この記事では中学受験において成績の良い子の特長を述べていきます。
逆に伸び悩む子の特徴も述べていきます。
成績が良い子は基本的に頭が良く、頭の良さは結局論理的思考力に尽きると思うのですが、それを書くと長くなるのでこの記事ではそこまでは踏み込みません。
以下に述べるのはあくまでも全体的な傾向ですので例外は沢山あります。
これから述べる成績が良い子の特長はあくまでも私が長年の塾講師経験で得た経験則で語ります。
何故そうなのかというのは憶測です。
成績が良い子の特長
私は塾講師経験は20年を超えていますが、成績が良い子には概ね共通した特長があります。
実際、中学受験で高い偏差値を維持できる子は「私から見て」頭が良いです。
では具体的に見ていきましょう。
①好奇心が旺盛
成績が良い子は大抵好奇心が旺盛です。特に理科や社会は興味がないと頭の中に染みこませるのに時間がかかります。
興味を持つ前提として好奇心があります。
そして好奇心があるかどうかが理科・社会の成績を大きく左右します。
好奇心があれば自然と知ろうと思い、知れば知るほど知らないことが増えて更に知りたくなるというのが学問というものです。
そして実はその好奇心は幼少期から育まれています。幼少期の子供の「なぜ?なに?」に答えることができたり、一緒に調べたりすることができれば子供の好奇心は育まれていきます。
正しく答えられるように大人も教養を身に着けておきましょう。教養を付けるのは大人になってからでも遅くはありません。
下記の理科教材は中学受験範囲までに特化した教材で、図解が非常に分かりやすいのでお勧めです。
社会の歴史漫画は集英社が入試によく出てくる近現代史が充実しているのでお勧めです。
②素直
成績が良い子は大抵素直です。例えば指導者が正しいノートの使い方や宿題のやり方を教えると、その通りにやってくれます。
中学受験の指導者にも無能な先生は沢山いますが、多くの場合は子供が考えたやり方より指導者が教えるやり方の方が正しいです。
それは「型にはめる」ということを意味しません。「細かいスペースを使って計算してはいけない」「眺めているだけでは覚えることはできない」といったごく常識的な勉強方法の指導に対しての素直さです。
③勉強のやり方が正しい
②の話と矛盾するようですが、そもそも成績の良い子は最初から大体正しい勉強のやり方をしています。そしてそれは誰に習った訳でもなく、自然と身についている子が多いです。
その上で細かい部分の指導については素直さが大事になります。
なぜ自然に身についているかと言うと、論理的に考えればそのやり方の方が成績を伸ばすには良いということに気づいているからです。
以下具体例を述べます。
ノートを贅沢につかう
これは算数において特に顕著です。成績が良い子は細かいスペースにゴチャゴチャ書くということをしません。
なぜなら間違えるからです。
途中式については「どこまで途中式を書くのか」「実際の試験の時にその途中式を書いている時間はあるのか」といった問題はあるものの、少なくとも宿題を解く時に途中式を省略する人は少ないです。
なぜなら後で丸付けをした時に自分が何を間違えたのかが分からなくなるからです。
何を間違えたのかを分からずに解き直しをしても効果は半減します。
その意味で消しゴムを「多用しない」のも成績が良い子の特長です。
できる問題はもうやらない
これは暗記科目で説明すると分かりやすいでしょう。
ものすごい簡単な例で述べます。
例えば県庁所在地を覚える時に千葉県の千葉市、宮崎県の宮崎市といったことは既に頭の中に入っているとしたらこれを繰り返し勉強する必要はありません。
島根県の松江市、香川県の高松市、愛媛県の松山市といった自分の中で定着していないことだけを練習します。
当たり前のことのように思えるかもしれませんが、これができていない人は実は結構います。
手を動かす
たしかに勉強の中にはyou tubeで天体の動画を観たり、歴史漫画を読んだりしてそれが勉強につながることは多々あります。
しかし成績が良い子は座学で勉強する時はとにかく手が動いています。
漢字を覚える時も社会の問題を解く時も手を動かします。算数の難問でも解き方が分からなくても取り合えず手を動かして条件を整理しています。
自習の時も成績の良い子ほど手を動かしています。「勉強って手を動かすことだな」と思えるほどです。
心配性である
林修さんの受け売りですが、ほとんどのケアレスミスの原因は思い込みと傲慢です。
成績が良い子は常に確認をします。「計算ミスしていたらどうしよう」「聞かれていることと違うことを答えたらどうしよう」「本当にこの考え方で良いのか」という心配をしながら問題を解いています。
成績の良い子は「自分は間違える人間である」という認識があるので常に確認をしながら問題を解いています。
心配性の人の方がケアレスミスは少ないです。
伸び悩む子の特徴
次に成績が悪くて伸び悩む子の特徴について述べます。(特長は優れた点で特徴は良くも悪くも目立つ点なので、これまで使ってきた特長も特徴も誤字ではありません)
伸び悩む子の特徴は簡単です。上記の成績が良い子の特長の逆が伸び悩む子の特徴そのものです。
つまり
・理科的な事象、社会的な事象に興味がない
・間違えたやり方を直さずひたすら頑固
・ノートの小さいスペースにゴチャゴチャと字を書く
・解いて丸付けすることが勉強だと思っている(本当はその後の解き直しや知識の定着が大事です。)
・手を動かさず考えているように見えるが実は何もしていない時間が多い
・楽観的で「自分は間違えない」という過信(傲慢さ)がある
まとめ
成績が良い子と伸び悩む子の特徴について述べました。結構思い当たる方も多かったのではないでしょうか。
好奇心は幼少期の環境に因るところが多いと言われています。幼少期の子の「なぜ?何?」に答えることができた親の子供は更に好奇心を持ちます。
その意味では親の教養がそのまま引き継がれているのかもしれません。
素直さも性格に因るところが多いので中々矯正するのは難しいところがあります。
ただ、勉強のやり方については直せるところもあるので実践できるところは実践されてみては如何でしょうか。
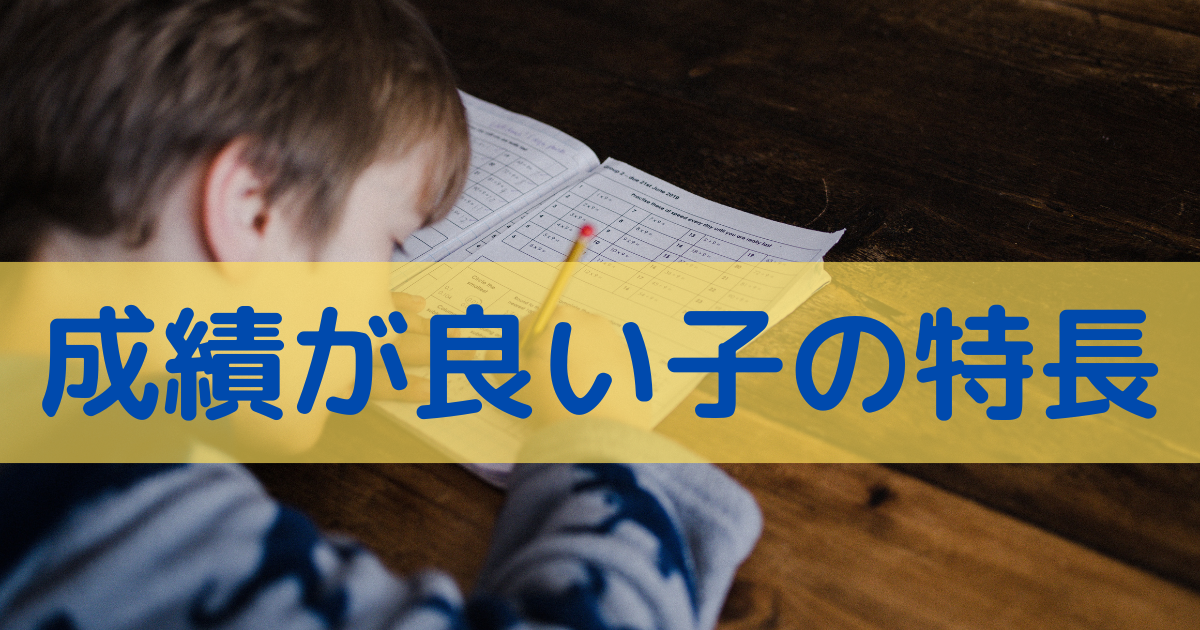






















コメント